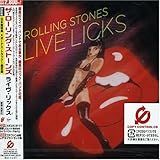
LIVE LICKS(CCCD)
80年代以降のストーンズのライブ盤では最高のものだろう。DISK1では「ストリートファイティングマン」「ギミーシェルター」の演奏の熱さ、荒っぽさが素晴らしい。DISK2ではブルーズ、R&Bのカバー曲が味わい深い。残念な点はいくつかの曲が短く編集されていることだ。オリジナル曲を聴きこんでいる人はDISK1を再生させて10秒後に違和感を感じることになる。 その後も何回かオヤっと思うはずである。(来日公演は原曲に忠実に行われていたし、LICKS TOURのDVDでは当たり前だが曲は短縮などされてはいない)市場むけにダラッとした部分をカットしたのだろうが、そのチンタラぶりこそストーンズの魅力ではないのか。その中にこそ彼ら独自のファンクネスは宿るのではなかったか。そこんとこ、うまくやってくれたら、屈指の名盤が生まれたとおもうのだけど。冒頭に「80年代以降の」とつけざるを得なかったのはそういう意味です。でも良い作品であることは間違いない。あと、ジャケを何とかしてくれ。

「ダーティ・ダンシング」オリジナル・サウンドトラック~アルティメット・エディション
映画の流れに沿ってかかった曲が入っているのでとても聴きやすかったです。昔の歌はいいですね。これから長く聴き続けていきたいです。

Very Best of Solomon Burke (Reis)
ディープ・ソウルの代表格として、思いつくのは誰でしょう?
オーティス・レディングか、ウィルスン・ピケットか、ジョー・テックスか。
もっと詳しければ、ガーネット・ミムズという名前を挙げる人もいるかも。
O.V.ライト? ジェイムズ・カー?
ですが、やはりこのソロモン・バークを抜いて考えてはなりません。
途中でゴスペルの世界へ行ったり、再びソウルの世界へと帰ってきたりしていますが、
その現在まで続く彼の足跡の中で、彼の存在を知らしめ、一般的にも最も知られているのは、
アトランティック・レーベルに在籍していた時期(1961-1968年)でありましょう。
このCDは、アトランティック時代のソロモン・バークの代表曲が16曲収録されており、
彼の音楽に触れる上で大変ありがたい1枚となっております。
別に、名前が有名だからとか、基本的な教養として聴いておかなければ、という学習意識からではなくて、
こういうものこそ、現在の耳で、現在の感性に即して、聴いていただきたいものです。
音楽の形式的に見れば、それは古臭いのでしょうが、
実に、聴き手の感情を強く揺さぶる世界が、そこにはあります。
そういうものは、いつまでも、世間がどうあっても、価値を持ち続けるものです。
そういうものを知りたければ、これを聴いて、絶対に損はしません。

Don't Give Up on Me
友人曰く「良いんだか悪いんだかよく分からない」~オジサン達にはこの気持ちがよ~く分かる。その要点の一つは、本作に対する世の中の注目がバークじゃなくて、ジョー・ヘンリーという白人青年のプロデュースワークや、白人ロックのビッグネームによって提供された楽曲にあることだろう。
で、その曲を聞いていくと、サザンソウルクラシックの名ソングライター、D.ペンによる1曲目は可もなし不可もなし。V.モリスンの2曲はモリスン節爆発で、彼のファンには喜ばれるだろう(私はファンじゃないのでトゥーマッチ)。T.ウェイツとコステロの曲はバークにはミスマッチ。ディランの提供曲は変哲のないブルースだが、バークは気持ち良さそうに歌っている。N.ロウのカントリー風のバラードは佳作だ。B.ウィルソンの曲はあまりバーク向きとも思えないが、タイトルから60年代してて楽しめる。マン=ウェイルによる最後から2番目の曲は、本作のベストトラックだろう。ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマをバックに、ヴォーカルの力でスウィングさせてくれる。自然なこぶしにシャウト、ヴォーカルミュージックとしてのゴスペルの魅力に溢れている。
こうやって聞いてくると、多少窮屈そうだったり、よそゆきぽかったりするものの、バークってのは歌がうまいな(かつては、うますぎて退屈なんて思ったけど)。あまりバックの音をいじらずに、バーク本来の歌の力を引き出した功績はジョー・ヘンリーに帰するだろう。ただジョーの自作曲だけ彼のソロ『スカー』やC.ウィルソンのブルーノート盤を思わせて、これはこれで面白かった。次作をこの路線でプロデュースすると、バークの新たなデモーニッシュな魅力がでるかもしれない。
最後の1曲は私の知らないライター(バークの変名?)によるが、掉尾をかざる素晴らしいソウルバラードだ。

Nothing's Impossible
アル・グリーンの甘く囁くようでいながらとてもソウルフルな声とウィリー・ミッチェルのゆったりと締まった音作りが素晴らしかったハイ・サウンドと、ロックン・ソウルの王様ソロモン・バークとの出会いは今までありそうでなかったものです。その出会いがようやく2008年の終わりになって実現してできたのがこのアルバムです。抑制的で間を重視するハイ・サウンドと饒舌気味なソロモン・バークとの相性はどうか?というのも杞憂でした。いいものといいものを足したらいいものだった、という単純明快なものです。最初の曲からあのじわじわ来る音と自在な歌声が聞こえてきます。ウィリー・ミッチェルのアル・グリーンとの近年の曲作りでもあった楽器のソロの強調とブルース色の濃い曲もあったり、ソロモンもDon't Give Up On Me以降の渋みが加わったりしますが、基本的には昔と同じことをやっています。それでもウィリー・ミッチェルは最晩年と思えない力の入り方で、ソロモンもそれに見事に応じているのが素晴らしいです。





