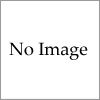
暗殺の森 完全版【字幕版】 [VHS]
G.ドルリューの、映像を超えず、映像に劣らずの寄りそった音楽。主役はJ=L.トランティニアン。絶頂期の作品だ。吹き替えのように聞こえるが、列車内でのラヴ・シーンなどは、トラウマなどの諸々の要素があいまって、かつトランティニアン独特の静かにも激しさを備えたものだ。彼の視線の先に映っているもの。あの知的な目がまたいい。忌まわしい過去に悩まされながらも、暗殺の使命を担って何か新しい世界へたどり着こうとする複雑な役。競演はS.サンドレッリにD.サンダ。このサンダ。撮影当時はまだ10代のはずだが、なんと言う官能美だろうか。あの緑色の瞳。そしてファッションの着こなしの素晴らしさ。

暗い森―神戸連続児童殺傷事件 (朝日文庫)
あらゆる観点から客観的に事件を追っているところがいい。とくに前半、動物虐待から通り魔事件へ、そして少年の妄想や願望がどのようにあの忌まわしい淳君殺害にいたったか丁寧に分析しているところがよかった。

黒い看護婦―福岡四人組保険金連続殺人 (新潮文庫)
著者は「黒い看護婦」達の生い立ちから、殺人事件へ至った背景へと
話を展開させますが、個人的には、このような話は特殊ではなく
「どこにでも起こりえること」と思いました。
というのは、女性が複数でつるむときの行動や心理が、
自分の職場の状況と非常によく似ているからです!(笑)
「女性だらけの職場には就職するな!」とよく言われますが、
それをリアルに描き出した傑作だと思います。
男としては、女性集団(女性一人一人では問題ない)の、
お局を筆頭とする陰湿・残虐な行動には、
興味よりも、ただただ嫌な気分にさせられます。
だから・・・いや、なんでもありません。
(**)

暗殺者の森 (100周年書き下ろし)
本当に心待ちにしていた一冊。逢坂さんはもう北都のこともヴァジニアのこともわすれてしまったのかな、と不安になったこともありましたが、ようやく、です。
「七月二十日事件」〜「ヴァルキューレ作戦」発動のあたりが今回の話の中心です。と、偉そうに書いても第二次大戦の欧州の動向について全く無知で、初めて知った内容でしたが。
ただこのイベリアシリーズを北都とヴァジニアのラブストーリーとして読んでいる私にとっては、ふたりの全く関与しない事件の記述が本書の大部分を占めており、教科書を読むような(退屈な)時間ではありましたが、舞台がベルリンと言うこともあり、特に後半にかけて、単なる脇役と思っていた尾形が大活躍をしてくれました。
胸を熱くさせるような前作のラストシーンから、本書では多少なりともふたりの関係が深まるのを期待していたのですが、さずがヴァジニア、あそこまでの目にあっても、決して負け犬にはなりませんでした。不屈です。ジェームズ・キャメロン映画のヒロインにもひけを取りません。今や彼女の「敵」は英国内部にあり、その敵を暴き出すべく戦うのです。
でもそのヴァジニアにして、どんな逼迫した状況であろうともナオミには張り合ってしまう可愛らしさ。
本当に強くて本当に可愛らしいヴァジニアが、変わらず本書にもいました。
個人的に猛反省しているのが、前作を読んだあと堪えきれずに、実在する主要な登場人物の「その後」を、軽率にもネットで調べてしまったことでした。無知なまま知らずにいれば、ふたりと一緒になって、歴史の展開に立ち会うことができたものを。「よく知らない」という方には、ぜひそのままで、本書の展開の中で知っていくことをお薦めします。
そして本作も、最後の最後に、息が止まり、知らずに涙が流れてしまいました。
こんな狂おしい気持ちで、次作を何年待たなければならないのでしょう。
でも、ドイツ、日本の敗戦まであとわずが。完結してしまうのも悲しい。
「百舌」の新作と併せて、じっと静かに待ちたいと思います。

暗殺の森 Blu-ray
『暗殺の森』('70)原題「il Conformista(英題:The Conformist)」。
1930年代末、ファシスト政権が台頭するイタリア。体制に順応して“普通の人”として生きていこうとするマルチェロ(ジャン=ルイ・トランティニャン)は、知性も魅力もないプチブルのジュリア(ステファニア・サンドレッリ)と婚約し、友人のイタロを通してファシスト党への入党を望んでいた。マルチェロには、13歳の時にリーノ(ピエール・クレマンティ)という同性愛の青年に襲われそうになり、とっさに彼の銃を奪って撃ったという苦い過去があった。「殺人を犯した」という罪の意識がトラウマとなり、意志を持って行動できない男になったマルチェロは、ただ体制に順応し、無感情に生きる。
やがてマルチェロは、党から秘密任務を受ける。それはパリに亡命している彼の恩師で、反ファシズムの指導者、クアドリ教授(エンツォ・タラショ)の暗殺だった。新婚旅行を利用してパリに赴いたマルチェロは、クアドリ教授と再会。彼の妻で若く美しく、挑発的なアンナ(ドミニク・サンダ)に、はじめてマルチェロは自分の心が騒ぐのを感じる。自分の任務に怖れを抱くマルチェロ。しかし、暗殺実行の時は無情に迫っていた・・・。
原作は、イタリア現代文学を代表する作家(画家ではありません。解説文は間違い)アルベルト・モラヴィア。戦中はファシスト政権に執筆活動を禁じられ、戦後はネオ・リアリスモを代表する作家になった。原題「il Conformista」の意味は「順応主義者」。異端になることを恐れる故に、自らの意志を持たずに漫然と社会に適応するだけの主人公を指す。自らの人生まで捏造してしまった男の、空虚極まりない生き方を通し、ファシズムが台頭・蔓延していく背景にあるものは独裁者と権力だけではなく、「順応主義」という民衆の無責任な心理・行動も然り、という事を仮借なく暴き立てる作品である。
本作で有名な逸話のひとつに、マルチェロが暗殺を命じられる恩師の住所が、ゴダールの住所と同じ(電話番号が同じという説もあり)という話がある。「ヌーヴェル・ヴァーグの父(ゴダール)をイタリアの末弟(ベルトルッチ)が殺した」と監督自身が言うように、本作は若きベルトルッチが受けてきた様々な影響、そして時代への決別表明の作品なのである。「インテリの独り言」から「観客との対話」へ。それは、この後に作られた映画を観れば如実に判る。
本作は、ファシズムが台頭する社会の閉塞感を、一見豪華絢爛に視えるアール・デコの時代を硬質で冷たく、そして人物は無感情に描く事で表現している。とにかく、主演のトランティニャンはじめ、俳優たちの感情をほとんど露わにしない無機質な演技は、観客としても感情移入できるキャラクターがいなくて困ってしまう(笑)。特に『1900年』('76)と比べてみると、同じ女優の演じるキャラクターの何と違うことか!平凡でつまらない、マルチェロの妻ジュリアを演じたステファニア・サンドレッリ。メイクも、いかにもこの時代のドーラン厚塗りで目の周りは黒く縁取り、クスクス笑ってばかりのお行儀の悪さを除いては、まるで人形のようだ。しかし『1900年』では、農民たちを鼓舞してファシストを倒そうとする女教師を実に生き生きと演じている。同じく本作では、ファム・ファタールともいえる役割を演じ、中性的な存在でジュリアすら誘惑するかの如き役を演じたドミニク・サンダは、『1900年』では納屋でデ・ニーロと全裸体当たりのラブシーンを熱演、波乱の時代の中で翻弄され、苦悩する等身大の女性を演じている。
そう、『暗殺の森』は、どこまでも硬質で冷たい、シニシズムの映画なのである。そして、「父親殺し」を宣言する監督自身の陰鬱な心を投影するかのように、滅び逝くファシズムの甘美の最後の残滓が、異常なまでの輝きを放ちながら映像に凝結している作品でもあるのだ。
とにかく、計算され尽くされたとも言える映像美には付け入る隙がなく、息が詰まるほどの思いである。
『地獄に堕ちた勇者ども』を意識していたベルトルッチに、撮影監督のストラーロは「我々だけの映像を創り上げよう」と言ったという。しかし「前半は白黒映画のようだ」とストラーロ自らが述懐するように、明らかにドイツ表現主義、あるいはオースン・ウェルズの映画を意識したとおぼしきアヴァンギャルドな構図や照明設計が展開する。斜めに傾いだ構図まで登場し、さすがにそれはやりすぎなのではと苦笑したくなるカットまであるのだが、色彩を極度に押さえた画面設計は、ファシズムの冷徹な時代の空気を見事に表現している。
この映画のアートセンスは本当に注目に値するのだが、中でも息を呑むのが建築である。まるでこの映画のセットとして造られたとしか思えない威圧的なモダニズム建築の数々。登場人物たちの背後の壁や意匠や空間が、もうファシズムを無言の裡に語っているようなのだが、それもそのはず、近代のイタリア建築の歴史は、ファシズムと切っても切れない縁があるのである。
20世紀初頭から、「未来派」―「ノヴェチェント」―「イタリア合理主義建築」の流れを汲む近代イタリアの建築様式は、皆ファシズムのプロパガンダとして利用された芸術運動だった。ファシスト政権下では、労働組合に替わりファシストがコントロールする「協働組合」というシステムが敷かれ、イタリア建築家協会はファシスト建築家協会となった。つまり建築家でありたいならば、ファシスト党員になるしかなかったのである。激動する時代の波の中で革新を続けるスタイル=破壊的でアナーキーな「未来派」、それに対し伝統と新時代の精神の合一を図った「ノヴェチェント」、反アカデミズム・機能主義を標榜した「イタリア合理主義建築」=は、ファシズムの社会構造と共鳴し、何よりも雄弁にファシズムを象徴するものになってしまったのだ。故に、この時代に活躍した建築家たちは、戦後、イタリアでの評価が遅れる事になる。
こうした、イタリアのモダニズム建築を絶妙に取り込んだ、ベルトルッチ&ストラーロの「視覚的共犯関係」は必見。ヴェンティミリアの町で、マルチェロが薔薇の花束を手に、ラテン語が一面に刻まれた壁に沿って歩くシーン。父親と面会する精神病棟 ― だだっ広いのに、不安感を掻きたてるその空間感覚。特にこの映画前半は、他に類を見ない完成度の映像だと断言していい。
そして衣装。上流階級の黄昏を暗示しつつも、アール・デコの時代ならではのスタイリッシュで絢爛たるファッションはやはり目を見張らざるを得ない。映画が製作されたのは、'60年代の終わり。パリでは学生運動が巻き起こり、時代の主役もまたブルジョワから「怒れる若者たち」へと代わろうとしていた。こうした「リアルな時代」と「映画の中の時代」の変化がシンクロし、古き時代への決別そしてレクイエムへと本作は昇華していくのだ。
滅び逝くものの虚無感と美しさを共存させつつ、『暗殺の森』は時代の境界を漂流するシネマなのである。
最後に、気になるのが本ソフトが「完全版」かどうかである。というか完全版でなかったら噴飯物なのだが(尺からみると完全版のようだが、しっかりと表記してほしい)。
初公開時にカットされていた4分ほどのシーンを、96年にベルトルッチが復元。それは盲人たちが地下で行う、「花嫁がいない結婚パーティー」である。マルチェロのファシスト党入党が暗示されていると言われるこのシーンが抜けているバージョンではないことを祈りたい。
完全版は、ストラーロの監修で、色彩などを最良の状態に復元したバージョンでもあるのだから。
とにかく再発に拍手。そしてぜひ「完全版」の表記を乞う!









