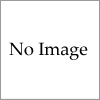
死の棘 [VHS]
俊雄の恋愛は事実であった。疑惑の中で耐え続けた妻ミホ。
「苦しめたくないのに苦しめてしまう」女を演じるのは松阪慶子、苦しめられる男を演じるのは岸本一徳。
勝手にわいてくる疑惑。愛と責め、男と女。太平洋戦争のまっただ中であった二人。特攻隊島尾中尉殿は出撃命令が下されなかった。ミホの感情の変化は激しい。言葉は棘として突き刺さる。問いつめる女。こたえる男。二人をみつつ育つ子ども二人。小康状態。年始の挨拶。様式化されている新年の儀式。ぼくはこのような様式を求めてきたのか。「お母さんの田舎に帰ろう」と男は子どもたちに語る。場所は奄美大島に移る。
大学病院を受診する、入院する。
帰ってくる妻ミホ、うけいれる俊雄、こども二人。
元愛人がきて、追いかけるミホ。近所のものたちが集まってくる。
子どもを奄美の名瀬にあずける、俊雄とミホは入院生活。持続精神療法がはじまる。
1時間55分の作品。原作者の島尾敏雄は69歳ですでに死去していた。

ガールフレンド (P‐Vine BOOKs)
子ども時代から30歳を過ぎた現在までの、同級生から年上の女友達、おばあちゃん、そして場合によっては男友達や犬・猫も含めた「ガールフレンド」たちとのかけがえのない瞬間、さりげない出会いと別れとが、抑えた口調で描かれた久々のエッセイ集。
居場所もつるむ相手もいなくて、意外にも疎外感に悩んでいたらしいオリーブ少女時代、ポスターの宇多田ヒカルと「妙齢感」を競ってしまう最近……。これは知っているあの娘だ、学生時代のあの子とおんなじ、もしくは自分に似ているかもとクスリと笑わされるかと思えば、なにげなく島尾敏雄・ミホ氏の名が出てきて、思いは一挙に彼女が受け継ぐDNAに飛んでいく。
奄美の自宅で一人亡くなったミホ氏の愛犬を探しあぐね、「ため息が腕にかかって、汗の跡がひんやりした」と表現する感性。自分の部屋をかたづけていて、「いつかわたしがいなくなった時、わたしを囲むこのガラクタが代わりに息をしてくれるかもしれない」と夢想する思い。彼女のブンガク的未来には、ますます期待を持ってしまう。
心地よい流れに身を任せているうちに、彼女の思い出、生活風景がこちらの頭に鮮やかに映し出されてくる。でも、巻末にあるように作品の一部はフィクションらしいから、そこにはキッチリ作家的な意図も入っているのだろう。特別にドラマティックなエピソードはないのに、読み終えたという満足感に気持ちよく浸らせてくれる不思議な作品集。

死の棘 (新潮文庫)
夜、夫婦が眠る前の場面で息が詰まる。10年におよぶ夫の裏切りを恨んでやまない妻はその子細を知りながら夫の口からすべてを告白させようとする。愛人たちの氏名や、彼女らに送った金品の金額。寝床での「尋問」は夫を眠らせず、妻自身も眠らない。夫にとって妻の異常を受け入れることは贖罪だが、自棄をおこして自殺や心中に焦がれるときもある。濃密な戦いのなかで神経をすり減らしていく夫婦の姿は、見てはいけないもののようで時にページを繰るのがためらわれた。妻は女の影を「ウニマ」といっておびえ、自身が深い内省に陥ることを「グドゥマ」と言い表す。彼女が生まれ育った鹿児島の離島の方言らしいが、その呪術的な響きは忌まわしく耳に残る。どれだけ相手を傷つけてもどれだけ許しを求めても、苦しみに出口は見えない。その傍らで日々の生活はつづき、子どもたちは育つ。すっかり狂気の世界の住人になれないところに、夫妻の最大の苦悩があるのかもしれない。

ナニカアル
実在の作家の幻の作品か?という設定がどれだけ魅惑的でしかしチャレンジングなものであるか、文学を志す者や小説を愛する者には分かってもらえると思う。私の5つの★の一つは先ずこの点にであり、逆にこの点や林芙美子や作品の描かれた時代背景に興味や知識のない方なら、絶対につけない★とも言える。
私自身、作者が林芙美子の文章を書ききるための労苦やその成果を十二分に受け止める素養があるわけではないが、平たく言えば「昭和の前半の桐野夏生の過激版」が描く世界と勝手に解釈して、本作に一気にのめり込んでいった。
この作品が作者の過去のテーマや内容に似ているとの評は表面的に過ぎる。作者は、己に通底する「ナニカアル」を芙美子に感じたからこそ、この作品を描き切ったと解する方が、この作品を素直に深く味わえるだろう。つまり、冒頭のような頭で読むアプローチが出来ずとも、他の桐野ワールド同様に、本能で感じ、肉体に味あわせることで、改めて頭の中に読むべきナニカが現れるはずだから。
とにかく読み切った後に己の中のナニカアルが感じられたなら、虚実の狭間にこそ本当のナニカがアルであろう本作の、実在の人物や史実を調べていって欲しい。そこにないものに、芙美子は、そして、作者は何を感じたのか?
実に味わいの深い作品だと思う。一読して★を5つにするのではなく、★が5つになるまで読み重ねる作品ということ。








