
ザ・ポピュラー・デューク・エリントン
自分自身もこれを一番最初に買って聞いた。
感想は「まぁ、こんなもんだろう」という感じで
可も無し不可も無し。ビッグバンド初心者ですから
そんなものですよ。そんなに何回も聞くものでも無し。
ずーと放って置いて、モダンジャズにのめりこんで
行ったのでした。それからウン十年過去の時代の
エリントンから遡ってまたこの「ポピュラー」に
たどり付きました。なんと新鮮で新しい感覚が
吹き込まれているのでしょう。改めて感心しました。
ですから、決して初心者向けでは無く、酸いも甘いも
噛み分けたジャズの達人向けとも言えるのでは無いで
しょうか。
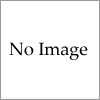
ビリー・ストレイホーンに捧ぐ
60年代のRCAにおける3作は何れも秀作だが初心者にはとっつきにくいと思う。
実際、日本ではRCAの三作は今まで紹介され続けて来たがエリントンのファン、いない、増えていない。
間違った入り方だと断言する。
つまりその洒脱や渋みや伊達といった形容が似合う作品の数々は、それ以外のエリントンに馴染んでいる人にはピンとくるが
そうではない人には単なる所持するためのアイテムにしか成り得ないように思う。
ストレイホーンはソロイストとバンドのサウンドをマッチさせることに才能を発揮させた人物。エリントンにそれが出来なかったという訳ではなく、信頼され任されていたと言ってもいいだろう。
癖のあるソロイストの魅力を十分に発揮させた挙句、過不足なくバンドのサウンドを調和させ破綻なく演奏を展開させる終わらせる。言葉にすれば簡単だが、実践者としてはとてつもなく至難だ、言っときますけどオーケストラなんですよ。それが出来たことにエリントン・ストレイホーンの凄みの一端がある。
しかしながらこの作品ではソロイスト達がバンドのサウンドに呼びかけるようにして演奏しているように感じる。
それが感傷ではなく、純粋に渋みとして聞き手の心を突くところに、恐らくはこの作品の味があるのだろう。ソロイストがサウンドに呼びかけ、サウンドが浮き上がってくる快感。それを感じれるかどうかが鍵だ。
蓮の花は泥の中から咲くから美しいとされる。まるでエリントンのために書かれた曲のようじゃないか。
恐らくはそうなのだと思う。
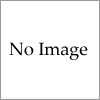
グレート・パリ・コンサート
74年に亡くなるまで前進を止めることのなかった、デューク・エリントンの63年のパリでのライヴ。実はこの時期のライヴ音源の多くがCD化されているがが、本作が内容的に最も充実している。
最大の聴きどころは、アナログ盤のA面に相当するTRACK1から6。デュークの長いピアノソロから一転、バンドを呼び込んで「これぞビッグバンド」のアンサンブルが咆哮する1から2、ジョニー・ホッジスの円熟のプレイが美しすぎる3、4、5、特に4の「STAR-CROSSED LOVERS」はオリジナル演奏を凌ぐ、というよりは本TRACKが最高の出来と思われる。そして再び怒涛のアンサンブルにしびれる6。
DISC2にボーナストラックがタップリ付属しますが、まあ、参考程度ということで。音質はオリジナルアナログ盤には敵わないので、オリジナル盤をお持ちのかたは、気軽に再生できる影武者的存在としてこのCDをお求めください。

レベッカ [DVD] FRT-001
この作品は、ヒチコック監督の代表作の1つであるが、映画のタッチは、むしろ製作者のセルズニックの色彩が濃く、「風と共に去りぬ」的なロマンティックな大作に感じられた。最も優れていると感じたのはアカデミー賞をとったジョージバーンズによる撮影の素晴らしさだ。冒頭の廃墟となったマンダレーのシーンから、モンテカルロの断崖、ホテルへの進行のうまさ。ところどころに挿入される海のシーン。原作の雰囲気を壊さず、スピーディーにこの映画を進行させ2時間の映画に終わらせたのは、撮影の絶妙さが欠かせないと思う。もちろん、1年前に若く無骨なヒースクリフを演じながら、今度は、正反対とも言える、偏屈な大富豪マクシムを演じきったオリビエ、新人でありながら、そのつたなさが主人公のキャラクターに見事に一致したフォンテーン、ワーグナーのライトモティーフのようににマンダレーや主人公、レベッカの暗示に使われる音楽の見事さなど、あらゆる要素が、この作品では、最高峰のレヴェルで発揮されてはいる。しかし今でもレベッカと言うと、マンダレーの屋敷を取り囲み込み、レベッカを死においやった海のシーンや、雨の中から登場する屋敷、最後に、Rの文字と共に燃えていく屋敷の場面が印象的な作品である。

Dispatches from the Edge: A Memoir of War, Disasters, and Survival
CNNを観る上で重要な本です。クーパー氏のこれまでが告白されています。氏のこれまでを知りたい方は、ご一読をどうぞ。







