
モーツァルト : ピアノ協奏曲第23番&第26番
一般的にはベートーヴェンのスペシャリストと云われているグルダだが、その本領はモーツァルトでこそ発揮される。
グルダのある意味「軽い」と云ったら語弊があるかもしれないが「軽妙」なタッチは、モーツァルトにこそ相応しい。
ジャズ好きだったグルダらしいアドリブを交えた演奏は、その美しいタッチと相俟ってまるでモーツァルトとの会話を楽しんでいるかの様だ。
天性のモーツァルト奏者による最高の「戴冠式」。
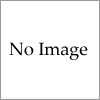
グルダの真実―クルト・ホーフマンとの対話
原著は1990年発行。対話と銘打たれているが、内容はグルダ(1930-2000)が自分のことを「縦横無尽、奔放に語る」という語り下ろし。おそらくはグルダへの数回、数年にわたってあちこちでおこなわれたインタビューをまとめたもの。著者のクルト・ホーフマンは放送局のディレクターという肩書を持つ1954年生まれの音楽ジャーナリスト。
さて、日本語に訳されたグルダの語りにあてられた“俺”という一人称。仮にもクラシック系の演奏家に“私”以外の一人称を使わせる訳文は、他にあまりお目にかかった記憶がない。が、読み進むにつれ、これが実によく「ハマっている」ことに驚かされる。
グルダの演奏というと、衝撃的と言われた最初のベートーヴェンのソナタ全曲録音からしてすでに、まずリズムありきで根源的であった。気迫に満ち、夾雑物がない。くっきりとした輪郭とモノクロームの世界へと引きこむような立体感が不思議と輝かしく、聴く者を圧倒する。そこには、あらゆることから自由(フリー)でありたいという焦燥感に満ちた魂が息づいている。本書での語りも彼の音楽そのままで、オフビートの力強さに満ちている。いままでずっと、この人は音楽それもクラシックの演奏であれほどに「語る」ことができるのに、なぜ異形扱いされながらもジャンルを超えてジャズやフリーミュージックへも手を出し、なおかつ言葉で自分を語ろうとしたのだろうと不思議でならなかった。だが、この本を読んで、なんとなく胸に落ちるものがあったように思う。たかが本を一冊読んだだけでわかったような気になるなよという、グルダ本人の声も聞こえてきそうだが。
ウィーンさらに戦後しばらくの音楽事情や、彼がレパートリーとする作品および作曲家への興味深い論評、ブレンデル(手厳しいコメントの連続!)やアルゲリッチ(グルダのほぼ唯一の弟子)やフルニエをはじめとする演奏家について言及するその口調のなんと皮肉で爽快なこと!
昨今は音楽媒体がCDからネットでの配信へと切り替わる可能性を見すえてか、ヒストリカルな録音をあらためてリリースということが一気に増えた。グルダの音源もしかり。当人が本書で「音盤リリースをキャンセルして手元のテープはどこかへ行ってしまった」と言及しているモーツァルトのソナタの音源が彼の死後に発見され、2006年にリリースされたことは記憶に新しい。これからでも彼の録音を聴いてファンになるという人も増えていくのではないか、いや、増えてくれることを期待したい。入念なディスコグラフィを巻末につけたこの本もそろそろ増補版を出していただきたいものだが、さすがにそれは無理な話なのだろうか。
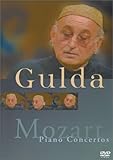
フリードリッヒ・グルダ・プレイズ・モーツァルト・ピアノ・コンチェルト [DVD]
グルダのモーツァルトには他にはない自由さがある。
弾き振りをするグルダは少々滑稽な姿(というか、身のこなし)だが、
その演奏には「モーツァルトが生きていた頃はこんな風に“自由に”演奏してのだろうな」と思わされる。
グルダの弾く音楽は自由で、生き生きとしている。
オケも頑張っている。
グルダの“生きた”音楽にただついていくだけでなく、ただ合わせるだけでもない。
グルダとともに、とても生き生きとした演奏を繰り広げている。







